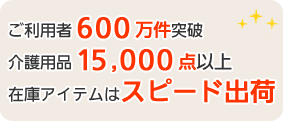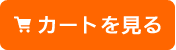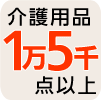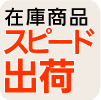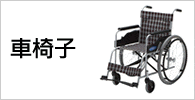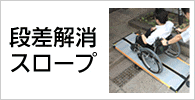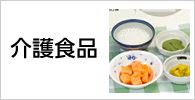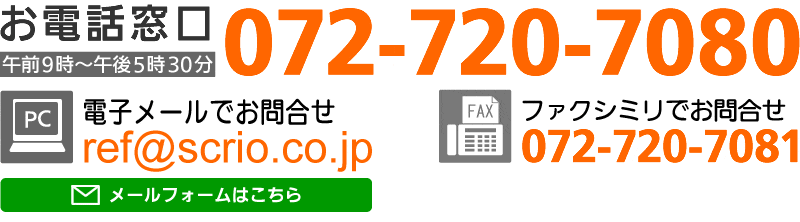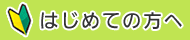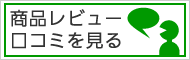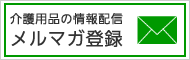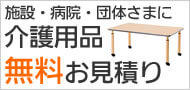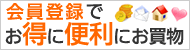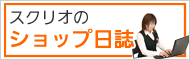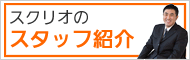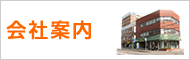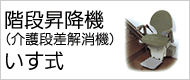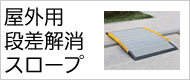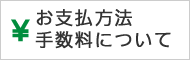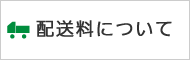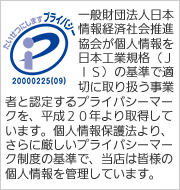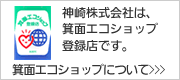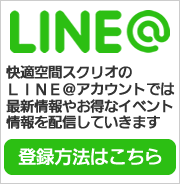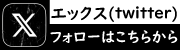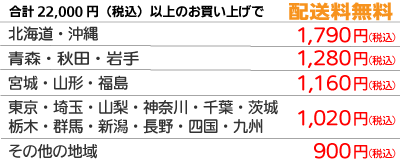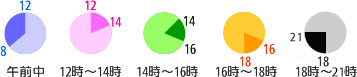手すりの種類とチェックポイント
「手すり」と一口に言っても、用途や場所によってさまざまな形状や機能のものがあります。
形状には、水平手すり(横手すり)・縦手すり・L字型手すり、くねくね曲がった波型手すりなどの種類があり、廊下・トイレ・浴室などに多く使われています。
出入り口用手すりや、玄関手すりなどと言った、設置する場所に特化した手すりもございます。
要介護状態の一割は転倒・骨折が原因です。
転倒予防の為にも、転ばぬ先の杖、もとい、転ばぬ先の手すりで手すりを設置するとよいですね。
手すりの種類と、選ぶ際のチェックポイントを説明いたします。
主な手すりの種類

浴室・洗面所手すり
立ち上がり補助手すり-

屋外用手すり
縦手すり(I型手すり)

縦手すりは、I型手すりとも呼ばれますね。
床面に対して垂直に設置するもので、出入り口や段差の近くに設置してします。
ドアを開け閉めしたり、段差をこえるときなどに、姿勢安定などの目的で多く使われています。
縦手すりの取付高さは、手すりの中心が「小さく前へならえ」をしたときの中指の高さが中心になるように取り付けるのが使いやすいとされています。
また、縦手すりの場合はしっかりと握って使うので、しっかりと握りやすい太さ。
ディンプル加工の手すりは、手すりに凸凹加工がされているので、
指がかかってしっかり手すりを握ることができます。
L字型手すり

L字型手すりは、水平手すりと縦手すりがひとつになった形と機能をもっています。
トイレや浴室、玄関など、便座やいすなどで「立ち上がり動作」を行うところでよく使われます。
取り付け高さは、トイレや玄関では、L字の水平部分の高さを通常の横手すりと同じ高さにします。
浴室では、浴槽での立ち座り用に
使うことが多く、
浴槽の上縁から10cmの高さに取り付けると使いやすいとされています。
L字型手すりもしっかり握って使うので、握りやすいものを選び、材質も冷たくならないものにしましょう。
波型手すり

病院や駅などで見かけたことはありませんか?
くねくね曲がった波型の手すりです。
この波型が、立ち上がるのに身体を引き寄せたり、踏ん張ったりするとき、握りやすい角度で握れるようになっています。
出入り口用手すり

オフセット型と呼ばれている手すりです。
ドアの近くに、手すりの握り部が位置する形状です。
ドアに近い位置に手すりがくるので、握りやすくしっかり身体を支えることができます。
床面から高さ1200mm前後あたりを握れるように取り付けます。
階段昇降用手すり

手すりは基本的に階段の両側につけますが、
片側にしか手すりを設置できない場合は、階段を下りる時に利き腕側にくるように設置します。
取り付け高さは段鼻から750mm程にします。
廊下の手すりと続いていない場合、なるべく手すりの端部は200mm以上水平に伸ばします。
これは手すりを持とうとして前のめりになることを防ぐためです。
光る手すり

名前のとおり、手すりが光り、暗くても手すりや階段の場所がわかります。
夜に暗い廊下を歩くときや、階段を上り下りするときに安心ですね。
手すり全体が光るタイプや、足元を照らすタイプもございます。
可動型(はねあげ・スイング)手すり

トイレなどで使用する可動する手すりです。
上にはねあげできたり、壁側から便器の前へスイングさせたりできます。
立ち上がり補助や姿勢保持として使われる手すりです。
使わないときはしまうことができるので、
トイレへの移乗の際や、ご家族が使用するときに邪魔になりません。
玄関手すり

段差のある玄関での昇降に使います。
段差の大きい玄関での昇降に不安がある方にオススメの手すりです。
玄関手すりを取り付けることで、身体の安定を保つことができます。
床に固定しなくても使える、工事不要の置くだけ設置の玄関手すりもございます。
賃貸や、さまざまな理由で工事ができない住宅におすすめです。
玄関台などと合わせて使えば、より安心して段差を上り下りをすることができます。
使いやすい玄関になることで、外出への意欲もわいてきますね。
手すりを設置する際の注意事項とポイント(水平手すりの場合)
ここでは、廊下・トイレ・浴室などにもっとも多く使われている水平手すりの設置について注意事項とポイントをご紹介します。
手すりを設置する際の注意事項
本人に確認しながら決める
使用される方が一番使いやすい位置で取り付ける事が基本です。
入院中の場合は可能であれば、一日仮退院して確認して決めるなどの配慮が必要です。
見本の手すりを用意する
本人が握って使いやすさを確認できるように、見本の手すりや棒(ほうきの柄、掃除機のパイプなど)を取り付け予定位置にあてがって、確認してもらいましょう。
手すりを設置する際のポイント
手すりの高さ
「高さ」とは、床面から手すり上面まどの高さのことです。
具体的には個人の状況にもよりますが、利用者本人の
大腿骨大転子の高さに2、3cm加えた高さがつかいやすいとされています。
杖の長さ目安と同じですね。 
テキストなどで、「75~85cmの高さにする」 などといった数値をよく目にしますが、これは不特定多数が使用する公共の建物などに適応する人間工学的な研究による数値なのです。
あくまでも「目やす」と考えるのがよいでしょう。
個人を対象とした住宅改修では、実際に棒などをあてがい、利用される方が確認してから、取り付け位置を決めましょう。
手すりの太さ
「太さ」は、握りやすいさ・使いやすさに関係する寸法なので、慎重に採寸しなければなりません。
これも利用者本人の手の大きさをもとにその太さを決めます。
目安としては、直径2.8~3.5cm程度が握りやすい太さと言われています。
握った時に指先が触れる程度の太さが目安です。
 手すりの形状は円形だけではありません。
手すりの形状は円形だけではありません。
リウマチなどにより、手すりを握ることが難しいときは、手すりに手や肘をのせて移動できる、楕円に近い形状になっている手すりを選ぶとよいでしょう。
手すりのあたたかさ
「あたたかさ」とは、材質の問題です。
特に屋外に設置する手すりは冷えやすいので、十分検討したうえで材質を選びましょう。
使う人に安心感を与えることが重要です。
材質的にステンレスなどの金属に 直接ふれるものは避け、その上に樹脂コーティングしてあるもの、プラスチック製のもの、また木製のものなどを選ぶことをオススメします。
表面にでこぼこをつけたディンプル加工付きは、指がかかってしっかり握れます。また、汚れを拭き取りやすいようにフッ素シリコン塗料をほどこしています。